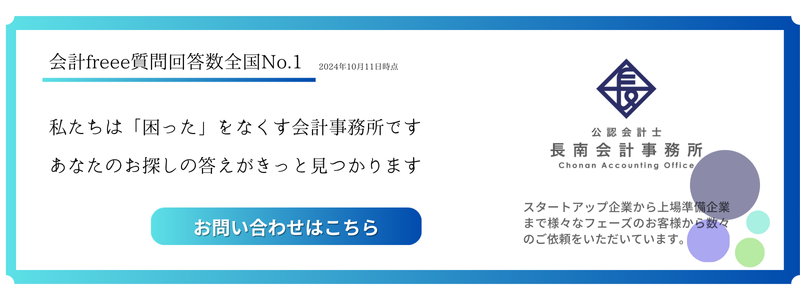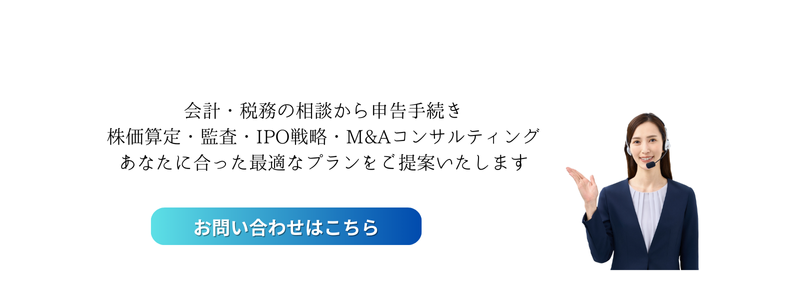役員報酬の決め方と節税の落とし穴
自分の会社の業績や規模であれば、そもそも
「役員報酬はどう決めればいいのか?」
会社の業績は当期はよくて、法人の納税額も多くなりそうだけど、
「役員報酬はどう決めれば節税になるのか?」
「不当に高額な役員報酬ってあるけど、税務署に否認されないルールとは?」
中小企業の経営者や個人会社の社長にとり、同業他社などと比較してどうなのか、役員報酬の設計は税負担を大きく左右する重要なポイントです。
しかし、間違った設定は節税どころかペナルティ課税にもなりかねません。本記事では役員報酬の決め方と見落としやすい落とし穴をわかりやすく解説します。
Contents
役員報酬の種類と基本ルール
税務上、役員報酬には、主に次の3種類があります:
- 定期同額給与:毎月同じ金額を支給する形式(もっとも一般的)
- 事前確定届出給与:賞与のように支給日・金額をあらかじめ届け出て支給
- 利益連動給与:業績に応じて変動するが、上場企業など一部法人に限定
中小企業の多くでは「定期同額給与」が基本です。これは期首から3か月以内に設定し、1年間は毎月同額で支給しなければなりません。1月だけ多かったり、少なかったりと、定期同額給与のルールから逸脱すると、その変更分は損金(法人の経費)にできなくなります。
損金・個人税・社会保険料のバランスがカギ

役員報酬は「多く出せば節税になる」ものの、同時に個人の所得税や社会保険料の負担も増えます。重要なのはこの三者のバランスです。
法人の節税効果
役員報酬は法人にとって損金算入可能(=利益を減らせる)なので、報酬を出すほど法人税は軽くなります。
所得税・住民税への影響
年収が900万円・1800万円を超えてくると、所得税率が23%→33%→40%と上がり、手取り率が一気に悪化します。これ以外に、住民税が10%課税されますので、最高税率においては、手残りが半分以下になります。1年間働いても、その半分は税金ということが実態となります。
社会保険料の圧迫
社会保険料は報酬額に比例します。年収1000万円の場合、年間150万円近くの社会保険料負担になることもあります。
ただし、標準報酬月額の上限は65万円となっています。
よくある落とし穴とその対策
落とし穴①:期中に報酬を変えてしまった
期中に報酬額を変更してしまうと原則、税務上否認となります。業績等の悪化である場合以外など、合理的理由のない変更は税務上否認となります。
対策: 年初3ヶ月以内に、1年間分の報酬を計画的に決定。
落とし穴②:届出をせずに役員賞与を出した
届出がなければ全額が損金不算入になります。仮に届出書を提出しても、記載された支給予定日から1日でもズレている場合や金額が異なっている場合には、税務上否認されます。
対策: 「事前確定届出給与」として、税務署への届出書類が必須。支給日と支給額のダブルチェック。
落とし穴③:社会保険料が想定外だった
社会保険料を加味せず報酬決定をしてしまうと、手取り額や会社負担分の社会保険が想定しているものとは乖離してしまったというのはよくある話です。
対策: 報酬総額ではなく「手取り後の可処分所得」でシミュレーションすることが大切。
節税のための役員報酬設計シミュレーション
例えば、ある会社で以下の2パターンを比較したとします。
| 項目 | パターンA(報酬80万円) | パターンB(報酬50万円+決算賞与) |
| 法人税額 | 減少 | 増加 |
| 社会保険料 | 約18万円/月 | 約11万円/月 |
| 手取り | 約55万円/月 | 約38万円+決算賞与次第 |
役員報酬を抑えて、事前確定届出賞与を活用したほうが、法人・個人ともにトータルメリットが出る場合もあります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 決算前に業績が悪化した場合、報酬を下げられますか?
原則不可。ただし「著しい業績悪化」等のやむを得ない事情があれば認められるケースもございますが、極まれです。
参考:国税庁
Q2. 節税だけ考えれば報酬は多い方がいい?
短期的な節税は可能でも、将来の資金繰りや借入与信、退職金積立に影響する可能性があります。また個人の所得税率も重要なポイントとなります。
退職所得の方が、現状では、手取額が多くなるため、リテンション施策も含め、人事制度全体の設計をする必要があります。
Q3. 家族に役員報酬を出すのは有効ですか?
所得分散による節税が可能。ただし、勤務や業務実態が必要。何もしない名義だけの報酬は否認されます。
まとめ
2025年の税制下でも、役員報酬は中小企業にとって最も効果的な節税手段の一つです。
ただし、制度は厳格で、一度のミスが数十万円以上の損につながることも。
報酬の設計には、節税・資金繰り・社会保険・将来の退職金など、複数の視点から総合的に判断することが重要です。
当事務所では、役員報酬のシミュレーション、事前確定届出書の作成、法人・個人の手取り最適化など、経験豊富な公認会計士が直接対応いたします。